オーサワの信州みそ
特集
信州味噌
味噌は、日本人が連綿と食べつないできたソウルフード。ほっとしたいときや疲れを感じたとき、はたまた和食からしばらく離れた日々を過ごしたとき。味噌汁がふと恋しくなり、口にすると安息して気持ちが満たされるのは、その味が私たちのDNAに刻み込まれているからではないでしょうか。
おいしい味噌をつくるためには、自動化や効率化とは対極の、麹と人間という、生き物同士の対峙が要。それは、1932年の創業以来、3代続いてきた「山万味噌」の信条でもあります。
文/野村美丘(photopicnic)
撮影/坂井竜治


つくり手の現場から
ー オーサワの信州みそ
ゼロからのスタート
右も左もわからない
ごはんからおやつまで、どんな食材ともマッチする万能調味料、味噌。かつては各家庭で手づくりされており、全国各地にその風土を反映したご当地味噌があります。なかでも信州味噌は、百年前の関東大震災の折、被災した首都圏に救援物資として送られ好評を博して以来、全国区に。今では国内で生産される味噌の半分以上のシェアを誇っています。
長野県岡谷市にある「山万加島屋商店」、通称「山万味噌」は1932年の創業。3代目で現当主の小松豊幸さんの祖父は、もともと製糸業に携わっていました。
「岡谷は当時、製糸業が盛んでした。食べ物が豊かではなかった時代で、工場の米と味噌汁のまかない食がおいしいと働き手が多く集まった。そこで大事にされたのが味噌。ボイラーがあって大豆を煮られ、仕込みができる広いスペースもあり、製糸工場には味噌づくりの条件が揃っていたんです」
ところが世界恐慌の影響で製糸業全般が赤字に。食べ物が乏しい世の中だからこそと、祖父は味噌屋への転身を決意します。同様の行動をした人は多く、岡谷は製糸に取って代わり、味噌で栄える街となりました。
しかし時代は下り、その数は徐々に減少。小松さんの父である2代目も、山万を廃業するつもりでいました。そんな折に父が病に倒れてしまいます。会社に残り、1代目から山万の味を守ってきた職人さんを、小松さんは手伝い始めます。「父は継がせる気がないし、自分もそのつもりは毛頭なかった」ものの、「山万のお味噌は本当においしいのだから、やめないで」という周囲からの懇願も後押しとなって一念発起し、家業を継ぐことにしたのでした。
麹づくり



このあと温度管理しながら米に麹の種付けをし、温醸庫で休ませる。

このあとさらに“夜の切り返し”を行う。
朝と夜の「切り返し」
「抜け掛け製法」と
麹づくり、大豆の仕込み、麹と大豆と塩を合わせて(混合)熟成と、味噌づくりには大きく分けて3つの工程があります。なかでも最も重要なのが麹づくり。いい味噌ができるかは麹の出来次第なので、山万では手間ひまを惜しまず、日々、丹念に麹づくりに取り組んでいます。
味噌づくりは、その麹づくりからスタート。まず、ひと晩浸漬した米を大釜で蒸します。山万で採用しているのは、米が均一に蒸せる“抜け掛け製法”。米を4層に分け段階的に蒸すことで蒸しムラを防ぐのですが、その時々の米の状態を見極めて浸漬と蒸しの時間を臨機応変に変えられる、職人の確かな腕が必要。また粉砕米や未熟米ではなく、良質な丸米を新鮮な状態で使うのは、そのほうが麹菌がうまくのるため。使用する米は基本的に信州産コシヒカリです。米が蒸し上がったら冷却し、麹菌の種付け。麹菌は高温すぎると死滅し、低温だと成長しないため、温度管理が重要で、適温は夏なら34℃、冬は36℃程度。ここでもやはり職人の経験が必須です。


麹を温醸庫に運び入れてひと晩おくと、麹菌の代謝活動で発熱し始めます。翌朝、麹室に移してから40℃以上になった麹を今度は冷まし、“朝の切り返し”作業。ここでいかに丁寧に固まりをほぐすかが麹の出来を左右します。
そのままだと熱がこもり温度が上昇してしまうため、同日の夜、温度を下げるべく“夜の切り返し”を行います。工場長の有賀順一さんが「いい麹になれよ~」と麹に話しかけながら、やさしくかつテンポよく、ショベルでまんべんなくひっくり返しては温度を計測。麹が醸す速度に人間が合わせ、細やかに見守る。ここまで丁寧に人の目と手をかける味噌屋は多くありません。
かなりの重労働でも「毎日やってると苦になりませんよ、むしろ楽しい。まあ、翌朝どうなってるか心配は常にありますけどね」と、有賀さんは笑顔を見せます。翌朝、ほんのり甘い栗の花のような香りがすれば麹がうまく醸された証拠。有賀さんがほっとできる瞬間です。
「いい麹でつくった味噌は、照りや香りが違う。商品として差がわかるほどではないけれど、生きている酵母を扱うかぎり、毎日の仕上がりにはどうしてもブレは出る。それをできるかぎり安定させるのが味噌づくりの永遠のテーマです」(小松さん)
オーサワの信州みそ、3種類の麹
米、発芽玄米、麦米、それぞれに麹菌を種付けすると、
見た目も味も違う麹になるが、いずれもいきいきと粒が立ち、美しい。
米麹

表面も中心部も真っ白で、栗の花のように甘い香り。
発芽玄米麹

麦米麹

風味と甘みの相乗効果で旨みがより引き立つ麹に。
あわせ味噌、発芽玄米味噌なども
山万ならではの味噌には
一般的にあわせ味噌というと2種以上の完成した味噌を合わせたものをいいますが、「オーサワの信州あわせみそ」は、麦と米を合わせてつくった麦米麹で仕込んでいます。
「2種類の酵素が合わさることで力強い麹になり、麦の風味と米の甘みで旨みを引き出したおいしい味噌に仕上がります」(小松さん)
そして3代目が開発した商品のひとつで、今や山万のオリジナリティを象徴する「オーサワの信州発芽玄米みそ」。発芽した胚芽のやわらかい部分から麹菌が入り込み、米の中心部が真っ白に。一般的に玄米麹は麹菌が入り込みやすいよう、表皮を少し削りますが、発芽玄米麹は玄米の表皮を削らずに麹にすることができます。
「玄米の甘みと旨み、香ばしさのおかげで、だしを入れなくてもおいしい味噌汁になります。キュウリなどにつけてそのまま食べるのもおすすめですよ」(小松さん)
味のよさだけでなく、食物繊維とGABAを含んでいるのも魅力。
味噌ができるまで





手間、工夫、心くばり
おいしい味噌にするための
大豆の蒸煮が完了したら、いよいよ味噌の仕込み。麹と大豆、そして天日塩を混合していきます。
「オーサワの信州白みそ(十二割糀木桶仕込み)」は、大豆10に対して麹が12の割合。一般的な西京白味噌より少ない割合なのですが、これは大豆の味と栄養を適度に残しているゆえのこと。味噌汁にしてもおいしく、味噌本来の特性を活かす、絶妙なバランスを狙っているのです。
仕込み味噌が完了したら、あとは熟成を待つばかり。天然醸造で半年以上寝かせ、麹がおいしい味噌に仕上げてくれるのをゆっくり待ちます。特に「オーサワの信州白みそ」は山万が創業以来使用している木桶でじっくりと熟成。百年ほど使い続けてきた杉樽の蔵付き酵母が山万伝統の味に仕上げます。
味噌屋を目指すために
感動していただける
味噌屋としての経験が皆無だった3代目が、はじめから順調なわけではありませんでした。大変な状況で体調も崩していたある日、気分転換に出た旅先のホテルで受けたもてなしに大感激した小松さん。「ああ、こんなふうにひとりひとりを大切にして、すべてに手間ひまをかけているからこそ、感動が生まれるんだ」と胸に響き、体調不良さえも吹き飛んだといいます。
この出来事をきっかけに「感動していただける味噌屋を目指す」ため、素材にこだわる、生産者の顔を見せる、アットホームなサービスを目指すなど、山万としての理念を明確に打ち立てるようになりました。
「売上だけを目標にするのではなく、山万の伝統と独自性に誇りをもち、お客さまのために最善を尽くして感動を届けたい、と考え方が変わっていったんです」

一番人気の発芽玄米ほか、緑大豆、黒豆の味噌など商品数が増え、売上も伸びていますが「規模はこのままで、中身をよりよくしていきたいんです。特に発芽玄米味噌など、小規模の手づくりだからこそつくれる味噌もあるし、お客さまひとりひとり、商品ひとつひとつに目を行き届かせ、大切にしたいので」と小松さん。
「味噌汁を飲んで、おいしさや安心感を感じる。そうした日々の小さな幸せをつくりたい。それに、こんなに簡単に多様な具材を食べられて栄養価のあるものはないでしょう? 昆布やしいたけ、野菜や豆腐など、味噌汁一杯で多くの生産者と関わることにもなります」
標高が高く寒暖差が激しいため、元来、天然醸造に適している岡谷。加えて山万では原料にもこだわっており、小松さんらが立ち上げた「大豆の会」で栽培している安曇野のナカセンナリをはじめ、国産はもとより地元・信州産の食材を積極的に使用しています。
「生味噌をもっと日々に取り入れてもらうことで、生産者を盛り上げ、かつ、豊かな食卓文化をつくっていきたいんです」
オーサワの信州白みそ(十二割糀 木桶仕込み)はこちら
オーサワの信州あわせみそ(麦米麹使用)はこちら
オーサワの信州 発芽玄米みそはこちら

小松 豊幸さん
合資会社 山万加島屋商店 / 代表社員
1932年創業。「山万の伝統と独自性で、ともに感動を創りだす味噌屋を目指し、豊かで幸せな文化を育む」を理念に、真心を込めたこだわりの味噌を生産している。信州産の良質な米や大豆、天日塩を使い、昔ながらの製法で白、赤、発芽玄米、緑大豆、黒豆などさまざまな種類の信州味噌を商品展開している。
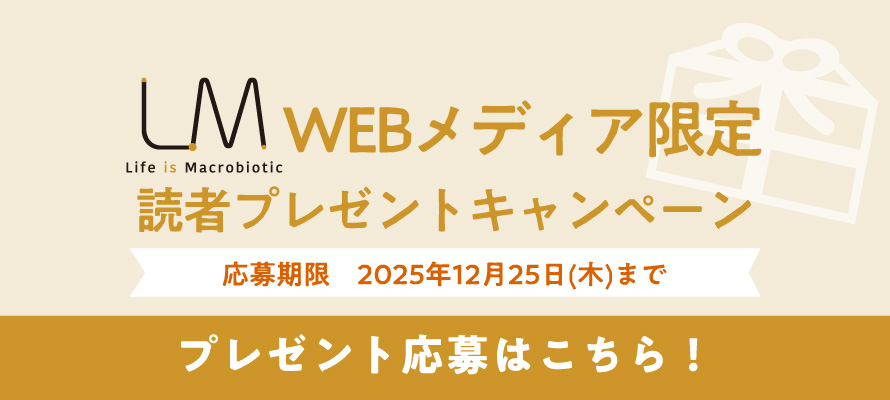

【LM WEBメディア限定 読者プレゼントキャンペーン】
WEBメディアLMをご覧いただいている方へ感謝を込めて、ご応募いただいた方の中から抽選で20名様に、LMvol.11特集「信州味噌」にてご紹介した味噌の中から、2種類をプレゼントいたします。ふるってご応募ください。
【賞品紹介】下記の賞品1・2を抽選でプレゼントいたします。
賞品1:オーサワの信州あわせみそ(麦米麹使用)
賞品2:下記よりいずれか1品(お申込フォームにてご希望を教えてください)
オーサワの信州 発芽玄米みそ
オーサワの信州白みそ (十二割糀 木桶仕込み)
*当選された場合でも賞品の数には限りがございますので、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
【応募方法】
専用お申込フォームよりご応募ください。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※賞品の発送は、2026年1月初旬頃の予定です。
【応募期限】
2025年12月25日(木)23:59迄
【ご注意】
・本キャンペーンのご応募は、日本在住の方に限らせていただきます。また、賞品の発送先も日本国内に限定させていただきます。
・賞品の換金および権利の譲渡はできません。
読者プレゼントキャンペーン専用お申込フォーム

ジャーナルの記事
マクロビオティックの仕事
食健 取締役 千坂義樹
私の祖父でもある千坂諭紀夫という人物がマクロビオティックの考え方をベースにした「千坂式食事療法」という食養生の実践を提唱し、その食養生の理論に沿った独自の玄米加工食品や、健康器具、基礎化粧品やサプリメントを販売する会社を興した創業者になり、私はその3代目ということになります。







